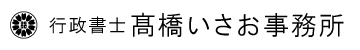民泊(住宅宿泊事業)のきほん
「施設を設け」、「宿泊料を受けて」、「人を宿泊させる」営業は、「旅館業」に該当し、原則として、都道府県知事の許可を受けなければその事業を営むことはできませんが、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づいて宿泊料を受けて人を宿泊させる場合、旅館業許可を受けずにその営業を行うことができます(=住宅宿泊事業、協議の民泊)。
この記事では、民泊の定義や要件、事業を行うための手続きなどについて解説します。
(なお、”民泊”の用語には、広義では住宅を使用する場合、旅館業許可を受けて行うものも含みます。また旅館業を受けずに行う特区民泊、イベント民泊等も民泊に含めて用いられる場合がありますが、この記事では「民泊」とは、住宅宿泊事業法に基づく事業を指すものとして記します)
目 次
住宅宿泊事業法による民泊とは
旅館業法に基づく旅館業は、宿泊者の安全や火災等の災害予防のため、旅館業法、建築基準法、消防法等でさまざまに規制されており、許可を受けて事業を開始するハードルが高く、旅行者の増減など需給の変化にタイムリーに対応することは簡単ではありません。
コロナ禍の時期を除き、近年は訪日旅客(インバウンド)の増加し、また景気回復に伴って日本人の国内旅行、ビジネストラベルも活発化しています。
このような状況や違法民泊の広がりなどに対応して、2018年に施行されてスタートしたのが「民泊」(住宅宿泊事業法によるもの)です。これは、住宅を活用した有償宿泊サービスの拡充により宿泊ニーズ拡大への対応を図るものです。
「民泊」事業は
- 宿泊料を受けて、人を「住宅」に宿泊させる事業であって
- 人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないもの
と定義されます。
それでは、上記の定義の確認から「民泊」の基本的な枠組みや手続きを確認していきましょう。
「民泊」における「住宅」とは
まず、有償で人を宿泊させる事業が「民泊」であるためには、宿泊される施設が住宅宿泊事業法で定める「住宅」に該当しなければなりません。要件を充たして「民泊」に供される住宅として届けられた受託を「届出住宅」といいます。
届出住宅となるために必要なことは
- 台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設
- 以下の“居住要件”のいずれかを充たすもの
ア.現に人の生活の本拠として使用されている家屋
イ.入居者の募集が行われている家屋
ウ.随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋 - 事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないもの
①③を満たして、かつ②のいずれかに該当すること、です。

住宅に必要な設備は?
必要な設備は上記のように、台所、浴室、便所、洗面設備です。
これらの設備は必ずしも独立して設けられている必要はありません。
すなわち、バス・トイレが一体となったユニットバスであってもよく、また浴室に浴槽が必ず必要なわけではなくシャワールームでもOKです。さらに専用の洗面台がなくとも、キッチンシンクと洗面を兼ねていても、例えば鏡がついていて洗面も可能であるなど、必要な設備を備えていると判断できる場合があります。
逆に、シンクのない場所を台所として電子レンジを設置すればいいか、というと、これは台所とは基本的には認められません(台所には流し(シンク))が必要)。
居住要件とは?
設備とは別に、対象建物の用途などの面から見た状況・状態が「居住要件」に該当することが必要です。それが上記②のア、イ、ウのいずれかに該当するかどうかということです。
ア.現に人の生活の本拠として使用されている家屋
あまり説明は必要とないと思いますが、平たく言えば「実際に人が住んでいる家」ということですね。少し詳しく言うと、実際に特定の人の生活が継続して営まれている家屋、とされています。そこに住む人の住民票の住所がおかれていることが多いですが、住んでいる人がその住所に所在する住宅を届出住宅として届ける場合は、その住宅は「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」と判断できます。ただし、必ずしも住民票がおかれているか否かをもって「現に人の生活の本拠として使用されているか」どうかが判断されるものではありません。
イ.入居者の募集が行われている家屋
「入居者の募集」というと、賃貸住宅をイメージしますが、ここでは賃貸住宅に限りません。
人が住む前提で分譲(売却)対象とされている(売りに出されている)物件、賃貸住宅として入居者を募集している物件、いずれも対象になります。
募集する入居者は、必ずしも世間から広く募集する必要はなく、例えば社員寮として入居希望社員の募集が行われているなど、入居対象者を限定している者であっても該当します。
ただし、家賃相場に比べて著しく高い家賃を設定している場合など、実質的に入居者募集の意図がないことが明らかである場合などは、これに該当しないと判断されます。
ウ.随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
このウに該当するものとしてイメージしやすいのは「別荘」ですね。生活の本拠ではないから空いていることも多いため、「民泊」として活用しよう、といった場合です。平日を都会で過ごし休日を郊外で過ごすなどのセカンドハウスも同様です。
他には、転勤で自宅を離れるが戻ってきたときにはまた住む予定の家、相続して所有することになったがすぐにはすまない(将来済む予定で所有している)家、などが該当します。
別荘の場合は少なくとも年に一回は使用していること、などが必要で、そのような使用実態がなく、また将来も居住する予定もない住宅は該当しないことになります。
事業の用に供されていないもの
受託の定義で見た「居住要件」にあるように、住宅宿泊事業は”住宅”を年180日の限度内で有償宿泊の事業に供するものですので、対象の住宅は「人の居住の用に供されていると認められるもの」とされています。そのため事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く)の用に供されている住宅は除かれます。
また、人を宿泊させる日数を年180日に制限している趣旨は、1年の残り185日は②の居住の用に供されることを前提としているため、人を宿泊させていない期間についても、人を宿泊または入居させる事業以外の事業に供することはできません。
ただし、民泊ガイドラインの「届出」の項目において…
「住宅」とは、1棟の建物である必要はなく、建物の一部分のみを住宅宿泊事業の用に供する場合には、当該部分「住宅」の要件を満たしている限りにおいて、当該部分を「住宅」として届け出ることができる。例えば、1棟の建物内で店舗と住宅といったように複数の用途が併存する建物においては、店舗部分を除いた住宅部分のみ「住宅」として使用することが可能とされているのであれば、その部分のみを「住宅」として届け出ることができる。
とされており、住宅と事業用部分が区分されているものの住宅部分を届出住宅とすることができる余地はあります(この点の判断は届出を受ける自治体によって行われるので、予め事前相談等で確認することが望ましいでしょう)。
1年で180日の限度
人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないという場合の1年間とは、4月1日正午から翌年4月1日正午までの1年間で、1泊を1日とカウントします。部屋が複数ある場合、1室でも宿泊させた日は1日と計算します。
管理業者への委託の要否
以下に該当する場合には、原則として国交大臣登録を受けた「住宅宿泊管理業者」に所定の管理業務を委託することが必要になります。
- 一件の届出住宅の居室が5室を超える場合
- 届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在となる場合
「民泊」には、”家主居住型”と”家主不在型”があります(次項参照)。
①に該当する居室数が5室を超えない家主居住型では住宅宿泊管理業者に管理業務を委託する必要はありませんが、それ以外の「家主居住型で居室数が6以上」の場合と、「家主不在型」の場合は、住宅宿泊管理業者に管理業務を委託することが義務付けれられます。
(ただし、住宅宿泊事業者が生活の本拠を置く住宅が、届出住宅と同じ敷地内または隣接して存在する場合で、自ら管理する居室が5以下であれば、家主居住型と同様に取り扱い、住宅宿泊管理業者への管理委託は義務ではありません)
家主居住型と家主不在型
家主居住型、家主不在型というのは法令上の正式な用語ではありませんが、、住宅宿泊事業法FAQ集によると、「一般的に、宿泊者が滞在している間に家主(届出者)が届出住宅にいる場合が「家主居住型」、住宅宿泊管理業者に委託し、宿泊者が滞在している間に家主(届出者)が不在となる場合が「家主不在型」と呼ばれています」とされています。
参考:家主とは?
上記のFAQには「家主(届出者)」とあります。また、民泊ポータルの「よくある質問」には、 「Q:法人が事業者の場合、従業員が常駐していれば、管理業者への委託は不要ですか?」 に対して、 「A:従業員は住宅宿泊事業者である法人ではありませんので、(中略)原則住宅宿泊管理業者への委託が必要です」と回答されています。
以上から、”家主”とは住宅宿泊事業者と同義と考えてよいと思われます。
それでは、「家主居住型」であるためには、宿泊者が滞在している間中、常に家主は度解けで住宅にいなければいけないでしょうか?
この点、家主が不在となる場合について、民泊ポータル等では「日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在は除く」としています。したがって、家主居住型の場合でも、家主の日常生活上の必要による一時的、短時間の外出は可能です。その時間は一概に何時間とは言えませんが、一般的には1~2時間程度と考えられ、仕事などで継続的、長時間不在になる場合には住宅っ宿泊事業者への管理委託が必要となります。
住宅宿泊管理事業者と委託業務
住宅宿泊管理事業者とは、住宅宿泊事業法に基づいて国土交通大臣の登録を受けている事業者です。住宅宿泊事業者で、管理をこの事業者に委託する義務がある場合は、1管理事業者に対象の管理業務を一括して委託しなければなりません。
管理を委託する業務とは、住宅宿泊事業者が行う必要のある業務(次項)のうち、①~⑥の業務です。
住宅宿泊事業者の業務
住宅宿泊事業者は、この事業を適正におこなうため、以下の業務を行わなければなりません(一部省略)。前項の通り、家主不在型等で管理を委託する場合の業務は、以下の①~⑥です。
- 宿泊者の衛生の確保
a.宿泊者一人当たりの居室面積を3.3㎡以上確保
b.定期的な清掃、換気の実施
c.宿泊者が入れ替わるごとに寝具のシーツ、カバー等を交換する - 宿泊者の安全の確
a.非常用照明器具の設置
b.避難経路の表示
c.火災その他の災害発生時の宿泊者の安全の確保のため必要な措置 - 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
外国語による設備使用方法、交通手段等の案内、情報提供等 - 宿泊者名簿の備付け等
- 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
- 騒音防止、ゴミ処理、火災予防等に関する説明(書面備え付け他の適切な方法で)
- 苦情等への対応
- 標識の掲示
- 都道府県知事への定期報告
毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における、次に掲げる事項を知事(権限委譲している市区においては、その市区長)に報告する必要があります
・ 届出住宅に人を宿泊させた日数
・ 宿泊者数
・ 延べ宿泊者数
・ 国籍別の宿泊者数の内訳
事業の届出
住宅宿泊事業を営むには、住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、都道府県知事等に届け出る必要があります。
実際の届け出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行います。
消防法令関係の確認
住宅宿泊事業を行う建築物は消防法令に適合する必要があり、原則として「消防法令適合通知書」を届出書に添付することが求められます。
届出住宅は消防法令上、「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」の規制が適用され、自動火災報知機の設置、誘導灯の設置、防火物品(カーテン、じゅうたん等)の使用や、一定規模以上の場合などに消火器の設置が求められますが、家主の居住型or不在型の別、宿泊室の規模・・・等によって免除されるもの、あるいは簡易なものでの代替できるものなどがあります(詳しくは別資料にて)。
その他、市町村条例に基づく届出が必要な場合があります。
欠格事由
以下の欠格事由に該当する場合は、住宅宿泊事業を営むことができません。
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 第16条第2項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から3年を経過しないものを含む。)
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が上記1~5のいずれかに該当するもの
- 法人であって、その役員のうちに上記1~5のいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
届出事項(届出書記載事項等)
住宅宿泊事業を営むための届出書には以下の事項を記載して、添付書類(次項目)を添えて都道府県知事(一部、市区町村に権限移譲さ)に届出を行ないます。
住宅宿泊事業は許可制、免許制でなく届出制なので、形式要件を充たした書類が所管行政庁に到達した時点で届出そのものは有効になります。ただし事業の開始には標識を掲示しなければなりません。標識は提出した書類の形式審査が行われてから交付されますので、実際の届出書提出から事業開始までには一定の日数がかかります。
届出書記載事項

添付ファイル

まとめ
民泊というと、騒音、ゴミ、マナーの問題等からネガティブにとらえられる場合も少なくありませんが、一方で訪日観光客数の増大は国の重要政策でもあります。つまり、オーバーツーリズムへの対策とともに、インバウンド受け入れ体制の拡充も求められています。
「民泊(住宅宿泊事業)」は受け入れ能力拡充の有力な方法の一つですので、課題認識ももちながら制度を有効に活用していく視点も大切になっていると思います。
当事務所では、健全な「民泊」事業のスタートを検討してる事業様へのお手伝いを行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
当事務所では民泊登録の他、旅行業関連の手続きについても事業者様へのお手伝いを行っております。