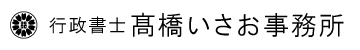法改正で危険負担はどう変わった? 契約書を作成するうえでの注意点は?
契約で用いられることの多い危険負担ですが、民法改正により法律の規定が大きく変わりました。今回は、民法改正を経て危険負担がどう変わったのか解説します。契約書を作成するうえでの注意点もあわせて解説するので、契約書を作成する際は参考にしてみてください。
目 次
危険負担とは?
通常、契約では当事者双方が相手方に対し債務を負っています。売買契約でいえば、売主は商品を引き渡す債務を、買主は商品の代金を支払う債務を負っています。
危険負担とは、契約当事者の一方の債務がその者の帰責性なく履行できなくなった場合に、他方当事者の債務を処理する際に用いられる考え方です。
債権者主義、債務者主義
売買取引の目的物が滅失した場合、その目的物を引き渡す債務を負うのは売主です。売買契約が成立した後、目的物の引き渡し前にその目的物が売主の責によらず滅失して引き渡しが不能になったとします。
この場合に、売主の目的物引き渡し債務は消滅し、買主の代金支払い義務が存続するとする場合、これを債権者主義といいます(=引き渡し債権の消滅の危険を負担するのは、引き渡し債権を持つ買主である、とするもの)。
反対に、上記の場合に売主の目的物の引き渡し債務が存続する場合を、債務者主義といいます。
特定物債権と種類債権
特定物とは、そのものの個性に着目して取引の目的とされるものを言います。例えば、中古車の場合、同じ年式・グレード・車名の車であっても、一台一台状態が違います。このように、そのものの個性に着目してそれを引き渡してもらう債権を特定物債権といいます。
これに対して、大量生産ラインで生産される家電商品をカタログを見て購入した場合、買主の債権はどの型番の商品を何個引き渡してもらう債権ということになり、どの個体を引き渡してもらうかということは通常問題になりません。このように、同じ種類のものの一定数量の引き渡しを目的とする債権を種類債権、といいます。
例えば、中古住宅(そのもものの個性に着目して取引される「特定物」)の売買契約を結んだ後、買主に引き渡す前にこの住宅が落雷による火災で焼失してしまった場面をイメージしてみてください。住宅が消失すると目的物には代替性がないため、売主(債務者)は住宅を買主(債権者)に引き渡すことができません。そして天変地異は売主・買主どちらのの責任でもありません。この場合に、買主の代金を支払うという債務はどう処理されるのか、というのが危険負担です。
旧民法の問題点
旧民法においては、原則は債務者主義がとられていましたが、特定物に関しては債権者主義がとられていました。
これは、不特定物の場合は引き渡し債権の目的物に代替性があるため、目的物の引き渡し債務が消滅する場合を想定する必要がないからでした。半面、特定物はそのものの滅失により、そのものの引き渡しができなくなるため引き渡し債務を消滅させる、としたものでした。
しかし、先ほどの中古住宅(特定物)の売買のケースで旧民法の債権者主義を取る場合は、買主には何の落ち度も無いにも関わらず“住宅引き渡しを受けられないのに、代金だけ支払わなければならない”となってしまいます。これは一般の人々の感情に照らしても納得性が高いものではありませんでした。実際の取引慣行上も、対象が高額な不動産などの取引では旧民法下では売買契約書に、「対象の建物の引き渡しをもって所有権を移転する」といった文言を入れ、個別取引において債権者主義を修正していました。
民法改正による変更点
以上に見たように、旧民法の特定物取引における債権者主義は、一般の人の感情や取引慣行にもそぐわず、実際の取引上も個別契約等で修正されることが多かったことから、新民法では危険負担を債務者主義に統一することとなりました。
民法改正による危険負担の変更点は3つあります。
債権者主義の削除
前述の通り、債権者主義は取引実務にそぐわないため改正により旧民法の債権者主義(旧民法534条、535条)は削除されました。
危険の移転時期の明文化
改正民法においては、目的物の「引渡し」時点が危険の移転時期であると規定されました(改正民法567条1項)。引き渡しをもって、目的物の滅失・損傷の危険(リスク)が売主から買主へ移転します。
効果が履行拒絶となった
旧民法において、危険負担が適用された場合の効果は片方の債務の消滅でした。
これに対し、改正民法においては、危険負担の効果は債務の履行を拒絶できる(履行拒絶権)こととなりました(改正民法536条1項)。中古住宅の売買の例でいえば、「目的の住宅が滅失しても代金支払債務は存続しており、買主は支払いを拒絶できるだけ」となります。そのため、債務を消滅させたい場合は契約の解除をする必要があります。
契約書を作成するうえでの2つの注意点
続いて、民法改正を踏まえて契約書を作成する際の注意点を解説します。

「引渡し」時期を明確に記載する
改正民法では、危険の移転時期を「引渡し」時点と規定しています。これ自体は取引実務に合致しており、前述のように、旧民法化でも契約書で債権者主義を修正するケースがほとんどでした。改正民法は実務を反映した形といえます。
とはいえ、「引渡し」とはいつか?という争いが発生する可能性はあります。そこで、契約書には、“どの時点のどんな行為をもって「引渡し」とするのか”を具体的に記載する必要があります。たとえば、不動産の場合でいうと、目的物が建物であれば「カギ」の引き渡しをもって建物の引き渡しとするというのが一般に行われる取引慣行だと思われます。
しかし、このように何が引き渡しであるかについて一般の慣行が成立しているものばかりではありません。従って、単に「引き渡した時点」や「検査完了時」と記載するのではなく、「所定の納品場所への搬入」や「検査合格証の交付」などというように、できるだけ具体的な記載を行うことが、後日のトラブルを回避するために重要なこととなってきます。
反対債務の帰趨を明確に記載する
民法の改正により、危険負担の効果が債務の消滅から履行拒絶に変更されました。
従来の契約書に「引渡し前は甲が危険を負担する」などの記載しかない場合、「危険」の内容が何なのか問題になります。「代金の支払いを拒絶することができる」というように、具体的な記載を心がけましょう。
まとめ
危険負担は売買や業務委託など多くの契約類型で用いられる概念です。取引実務を反映する形で改正が行われましたが、引渡し時点や効果など、契約書では具体的かつ明確な規定が求められます。不安な場合は専門家への依頼をおすすめします。
行政書士は、「権利・義務に関する書類」を作成することができる国家資格者です。皆様の権利・利益を守るため、取引や約束毎を行った際には、契約書を作成しておきましょう。
契約書に関するご相談、ご依頼はお気軽に下記までご連絡ください。
お気軽にお問い合わせください。048-799-2570受付時間 9:00-18:00 [ 月~土 ]
メールの方はこちらから 24時間受付中<関連リンク(当サイト内)>